(
烏帽子
烏帽子・冠・仮髪
(![]() ←マークの有る絵はカーソルを乗せると、変化します)
←マークの有る絵はカーソルを乗せると、変化します)
烏帽子
![]()
その他
| 頂が前方に尖り、しころが後ろに飛び出した形。鳳凰の頭をかたどったとされ、錦で出来ている。楽人・伶人の被り物。『梅枝』『大社』『道明寺』『富士太鼓』のシテに用いる。 | 山伏の被り物。無明煩悩を示す黒布で作られる。大日如来の五智宝冠を象徴する低い円柱に、十二因縁にちなんだ12のヒダをつける。山中の毒気にふれるのを防ぐという。 | 天狗役に使う兜巾で、金襴地で兜巾より大形に作られていて、赤頭の上につける。 |
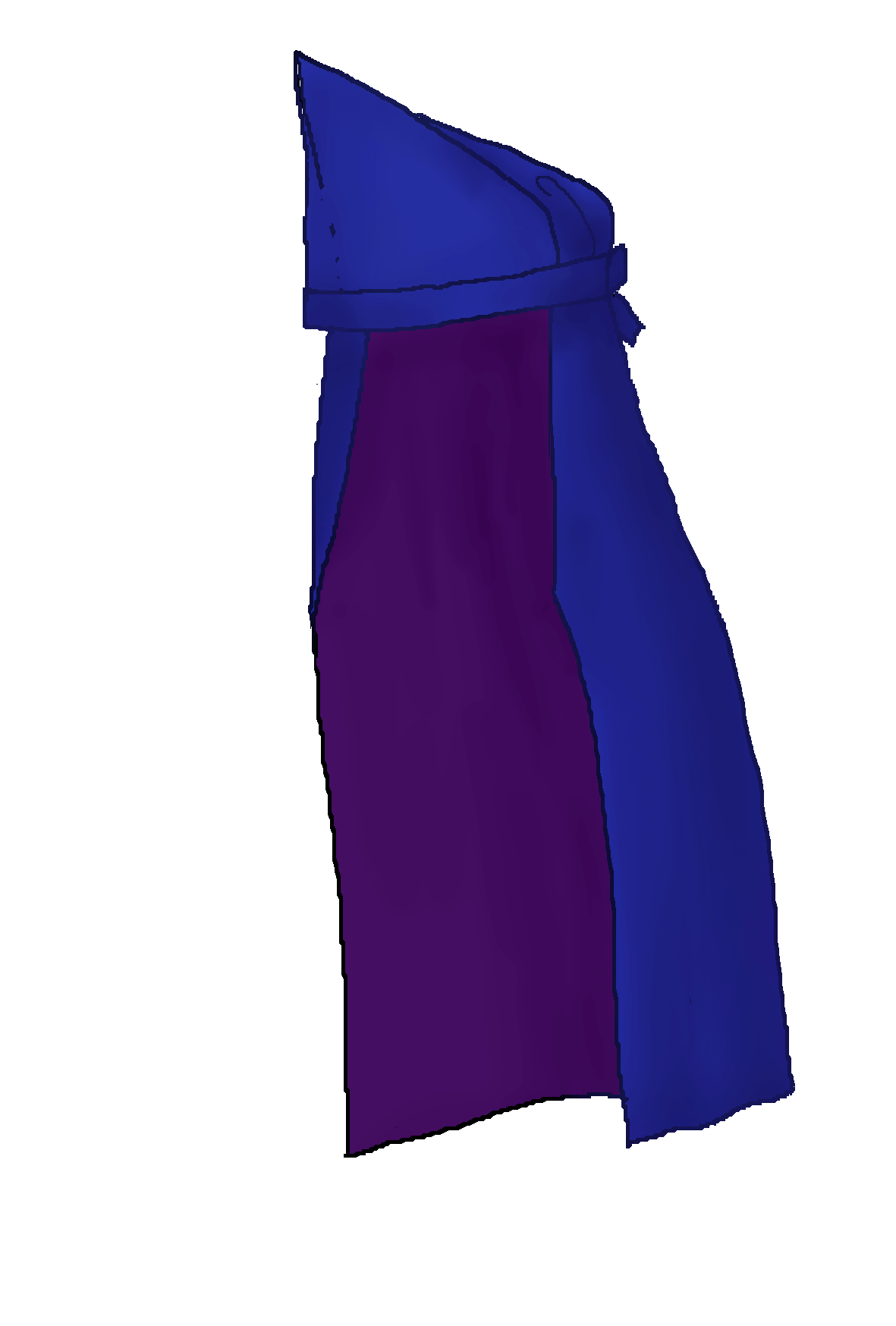 |
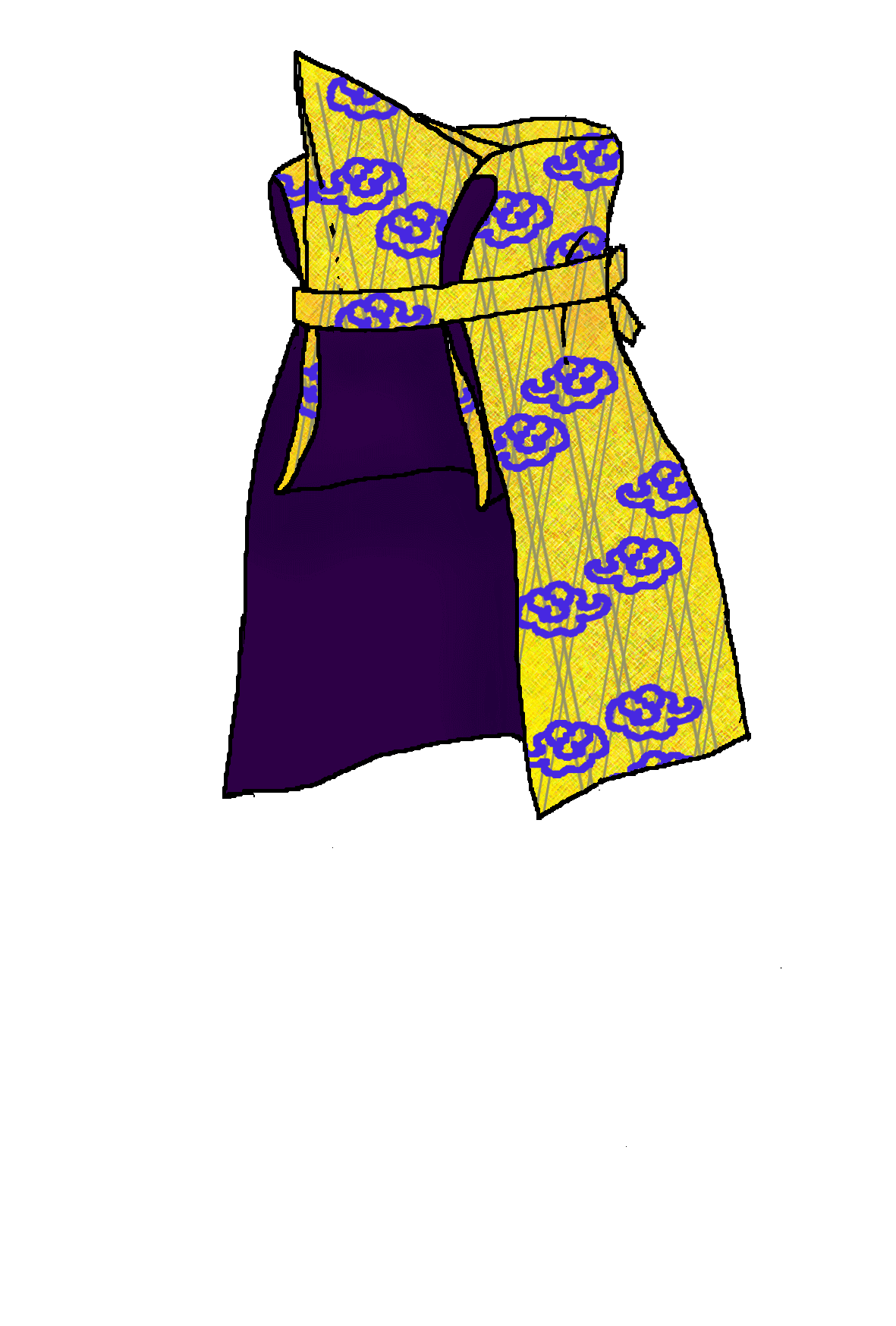 |
|
| 僧侶の役がかぶる頭巾の一種。紺、茶などの無地の緞子で出来ていて、頭部を三角形に尖らせ、後ろに長く垂らし、平紐で後頭部に結ぶ。ワキ・ワキツレの僧役や『熊坂』の前シテ、『景清』『俊寛』に用いる。 | 角帽子を折り込んで短く着る形で、布は金襴を使う。高僧の役に使われる。 | |
![]()
仮髪:鬘・頭・垂の総称。かつらの事
| 女性役の仮髪で、黒髪を左右に分け、耳を隠す様に後ろに流し、元結で結ぶ。 その上に鬘帯をして、面をかける。特に長い物を長鬘<ナガカズラ>と言い、天人や狂女に用いる。 更に長いかもじを垂らしたものを長髢<ナガカモジ>と言い、『葵上』の小書「空之祈」に用いる。 鬘の毛の一部を前に垂らしたものを付髪<ツケガミ>、又は乱髪<ミダレガミ>と言い、『蝉丸』・『玉葛』のシテに用いる。 |
|
| 老女の鬘で、色は白又はごましお。 | |
| 男役の鬘で、後ろを長くして結び、鬘帯をしない。 | |
| 老人の鬘。大きな髷で、髻の先が面の額にかかる。色は黄ばんだ白。 | |
(赤・黒・白) |
前髪を下ろし、横は肩、後ろは身長ほどの長い仮髪。 色が3色あり、役柄によって使い分ける。多くの場合、赤は神・竜神・天狗などに用い、特に2本の金無地扇をつけたものを獅子頭と言う。黒は童子・慈童・怨霊などで、これに金具の鍬形をつけて武将の幽霊にも用いる。白は老体・神霊・鬼畜などで、赤・黒より威力の有る年の功をつんだ者を表す(ただし喜多流の山姥は常に白頭なので例外)。 演出によって変わる事も有り、そのまま小書名として、赤頭・黒頭・白頭と表記する。 |
(黒・白) |
肩下まで垂らした仮髪。「頭」より短く、髪の量も少ない、髪裾が揃っている。 黒は「高砂」「田村」の後シテや男の神、天女や狂女にも用いる。白は「実盛」の後シテ、「西行桜」、『鷺』、『鶴亀』の亀役などに用いる。 |